「不動産投資は節税になる」――この言葉を耳にして、興味を持った方も少なくないでしょう。しかし、「減価償却」「青色申告」「法人化」といった言葉は聞いたことがあっても、それが具体的にどう税金に影響し、どこで差がつくのか、正確に理解している方は多くありません。
この第8回では、不動産投資における「節税」のメカニズムを、実例を交えながら基本から一歩踏み込んで分かりやすく解説します。
- なぜ「利益を減らす」と税金が減るのか?
- キャッシュが減らない「見えない経費」減価償却の魔法とは?
- 青色申告がもたらす強力な特典とは?
- 法人化は本当に節税になるのか? そのメリットと注意点。
これらの疑問を解消し、あなたが不動産投資で賢く節税するための知識を身につけられるよう丁寧に解説していきます。
ただし、税法は複雑であり、個々の状況によって最適な節税策は異なります。本記事は一般的な情報提供を目的としており、具体的な税務判断や手続きについては、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
節税の基本的な考え方
「節税」とは、合法的な範囲で税金負担を減らすことです。その基本は、「利益を減らす(=経費を増やす)」ことにあります。
なぜ利益を減らす(=経費を増やす)と税金が減るのか
私たちの所得にかかる税金(所得税、住民税)は、基本的に「所得(利益)の金額」に応じて計算されます。所得が多ければ多いほど税率が高くなる「累進課税」という仕組みが採られています。
税金の計算式(簡略版): 税金 = 所得 × 税率
ここでいう「所得」とは、「収入 − 経費」で計算されます。つまり、収入が同じでも、経費を多く計上することで所得が減り、結果として税金も減る、というシンプルな構造です。
不動産投資の場合、家賃収入が「収入」となり、物件の維持管理にかかる費用やローンの金利などが「経費」となります。この経費をいかに適切に計上し、さらに税法上の特例を活用して「見えない経費」を作り出すかが、節税の鍵となります。
キャッシュフローと税負担の関係
ここで重要なのが、「キャッシュフロー」と「税負担」は必ずしも一致しないという点です。
- キャッシュフロー:実際に手元に残る現金のこと。家賃収入から、ローン返済元金、経費(管理費、修繕費など現金支出を伴うもの)、税金などを差し引いた残りの現金。
- 所得:税金を計算するための基準となる利益のこと。収入から現金支出を伴う経費に加えて、現金支出を伴わない「減価償却費」などの会計上の経費を差し引いたもの。
不動産投資の醍醐味の一つは「所得」と「キャッシュフロー」のズレを利用して、税負担を軽減しつつ、手元のキャッシュはしっかり確保できる点にあります。
不動産・事業所得ならではの節税余地
不動産投資から得られる所得は「不動産所得」に分類されます。この不動産所得は、サラリーマンの給与所得などとは異なり、様々な経費計上が認められています。
また、ある一定規模以上の不動産賃貸事業と認められた場合(一般的に5棟10室基準)、その所得は「事業所得」に準ずる扱いとなり、青色申告特別控除の最大額や専従者給与の計上など、より大きな節税メリットを享受できる可能性があります。
個人事業主として不動産投資を行う場合、給与所得者ではできない節税策を活用できるため、節税効果を実感しやすい分野と言えるでしょう。
減価償却で赤字でも節税できる理由
不動産投資における節税の「肝」とも言えるのが「減価償却」です。これは、実際に現金が出ていかないにもかかわらず、税金計算上の経費となる「見えない経費」です。
減価償却とは「見えない経費」
減価償却とは、建物や設備のように時間が経つと価値が減っていく固定資産について、購入費用を一度に経費とせず、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して少しずつ経費として計上していく会計処理のことです。
例えば、1億円の不動産(土地5,000万円、建物5,000万円)を購入した場合、土地は劣化しないため減価償却の対象になりませんが、建物は劣化するため減価償却の対象となります。建物の耐用年数が50年であれば、毎年100万円(5,000万円 ÷ 50年)が経費として計上される、といったイメージです。
重要なのは、この100万円は、実際に銀行口座から出ていくお金ではないということです。購入時に一度に支払いは終わっていますが、会計上は毎年この金額を経費として認識することで所得を圧縮できるのです。
実際にキャッシュが減らないのに税金は減る仕組み
家賃収入が1000万円、現金でかかる経費(管理費、修繕費、ローン金利など)が500万円だったとします。 この場合、キャッシュフローは500万円のプラスです。
ここに減価償却費200万円を計上できるとどうなるでしょうか。
税金計算上の所得: 収入1000万円 − 現金経費500万円 − 減価償却費200万円 = 所得300万円
所得は300万円に圧縮されましたが、実際に手元にあるキャッシュは500万円のままです。 つまり、200万円の所得を減らした分、その分の税金が安くなるのです。 この「キャッシュは手元に残るのに、税金計算上の利益が減る」という特性こそが不動産投資の大きな節税メリットの源泉となります。
不動産投資のシミュレーション例
以下の条件で見てみましょう。
- 家賃収入:年間500万円
- 現金支出経費(管理費、修繕費、ローン金利など):年間200万円
- 減価償却費:年間150万円(建物部分が古い物件の場合など)
- あなたの給与所得:年間600万円(税率20%、住民税10%と仮定)
不動産所得の計算: 500万円(収入) − 200万円(現金経費) − 150万円(減価償却費) = 不動産所得150万円
仮に減価償却費がなければ、不動産所得は300万円になります。 減価償却費150万円のおかげで、所得が150万円圧縮されたことになります。 この150万円に対し、あなたの所得税・住民税率が合計30%と仮定すると150万円 × 30% = 45万円 の税金が減る計算になります。
手元のキャッシュフローは、 500万円(家賃収入) − 200万円(現金経費) = 300万円 のプラスです。 つまり、手元に300万円のキャッシュが残りながら、45万円の節税効果が得られるという仕組みです。
【重要事項】 減価償却費の計算方法は、物件の構造(木造、RC造など)、築年数、購入価格における建物と土地の割合によって大きく変動します。特に、中古物件の建物部分が古く、かつ購入価格における建物比率が高い場合は、短期間で多額の減価償却費を計上できる可能性があります。 正確な減価償却費の計算と計上には、税理士の専門知識が不可欠です。
減価償却費を大きく取れる物件の選び方
減価償却費を大きく計上できる物件には、主に以下のような特徴があります。
- 古い木造アパート・戸建て(法定耐用年数を過ぎた物件)
木造の法定耐用年数は22年です。築22年を超える木造物件は、「簡便法」という特殊な計算方法を用いることで、残存耐用年数が大幅に短縮され、4年で減価償却を終えることができます。 - 建物比率の高い物件
土地は減価償却の対象外ですが、建物は対象です。購入価格に占める建物部分の割合が高いほど、減価償却費として計上できる金額も大きくなります。 - 内装や設備費が高額な物件(事業用資産)
建物本体だけでなく、エアコン、給湯器、エレベーターなどの付帯設備も減価償却の対象となります。高額なリノベーション費用も、その内容によっては減価償却資産として計上できます。
【注意点】 減価償却費が計上し終わると、急に不動産所得の税負担が増えることになります。これは「出口戦略」や「次の投資」を考える重要なタイミングです。 また、減価償却を多く取った物件は、売却時に「帳簿上の利益」が大きくなり、譲渡所得税が高くなる可能性もあります。これらのバランスを税理士と相談しながら戦略を立てることが重要です。
青色申告の強力な特典
不動産投資で節税を考えるなら、「青色申告」の選択は必須と言えるほど強力なメリットがあります。
青色申告特別控除(65万円控除)
青色申告の最大の特典の一つが「青色申告特別控除」です。これは、事業所得や不動産所得から、最大65万円を差し引けるというものです。
白色申告との違い
- 白色申告: 特に税務署への届出は不要で、簡易な帳簿付けで済みます。しかし、控除や特典はほとんどありません。
- 青色申告: 事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。また、複式簿記というルールに従って帳簿を付ける必要があります。手間はかかりますが、その分手厚い特典が用意されています。
簡易簿記 vs 複式簿記で控除額が変わる
- 10万円控除: 簡易簿記(簡単な現金出納帳など)でも適用されます。
- 65万円控除: 以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 不動産所得が「事業的規模」であること(一般的に5棟10室基準)。
- 正規の簿記の原則(複式簿記)に従って帳簿を付け、その帳簿に基づいて貸借対照表と損益計算書を作成すること。
- 確定申告書をe-Tax(電子申告)で提出すること、または電子帳簿保存を行うこと。
65万円の所得が控除されるということは、その65万円にかかる所得税・住民税が丸々ゼロになることを意味します。税率によっては数十万円もの節税効果が見込めます。
【重要事項】 複式簿記での帳簿付けは専門知識が必要です。会計ソフトの導入や、税理士に記帳代行や確定申告を依頼するのが一般的です。青色申告承認申請書の提出期限(原則として、青色申告をしようとする年の3月15日まで)にも注意が必要です。
損益通算と繰越控除
青色申告は、他の所得との相殺や、将来の赤字の繰り越しにも威力を発揮します。
- 損益通算: 不動産所得が赤字になった場合、その赤字を他の所得(給与所得や事業所得など)と相殺できる制度です。 例えば、給与所得が500万円で、不動産所得が減価償却費の計上などにより100万円の赤字になった場合、全体の所得は500万円 − 100万円 = 400万円として計算されます。これにより、給与から引かれていた税金の一部が還付される可能性があります。 特に、購入初年度や大規模修繕を行った年度など、一時的に多額の経費が発生して赤字になりやすい不動産投資において、非常に強力な節税効果を発揮します。
- 繰越控除: 損益通算してもなお不動産所得の赤字が残る場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。 翌年以降に不動産所得が黒字になった場合、その黒字と繰り越された赤字を相殺することで、将来の税負担を軽減できます。
具体的にいくら税額が変わるのか
シミュレーション例を見てみましょう。
- あなたの給与所得:600万円
- 不動産所得:経費(減価償却費含む)により、年間50万円の赤字(青色申告特別控除65万円を適用する前の金額)
- あなたの所得税率:20%(所得税)、住民税率:10%(住民税)
青色申告なし(白色申告の場合):
不動産所得の赤字は、原則として給与所得とは損益通算できません(不動産所得の赤字のうち、土地取得に要した負債利子分は損益通算不可。それ以外の赤字は損益通算可能ですが、青色申告ほどのメリットがない場合が多い)。 したがって、給与所得600万円に対して税金がかかります。
青色申告あり(65万円控除・損益通算適用の場合)
不動産所得の赤字を給与所得と損益通算: 給与所得600万円 − 不動産所得の赤字50万円 = 550万円
青色申告特別控除の適用: 550万円 − 65万円 = 485万円(これが税金計算の対象となる所得)
つまり、青色申告をすることで、税金計算の対象となる所得が、給与所得600万円から485万円にまで大幅に圧縮されます。 この差額115万円(600万円 − 485万円)に対して、所得税・住民税合計30%と仮定すると、 115万円 × 30% = 34.5万円 の税金が節約できる計算になります。
【重要事項】 青色申告の適用には、事業的規模の要件や、複式簿記での記帳、e-Taxでの提出など、満たすべき条件があります。これらの要件を満たしているか、また具体的な節税額のシミュレーションについては、必ず税理士に相談し、適切なアドバイスを受けてください。
法人化のメリットとタイミング
不動産投資の規模が大きくなってきたら、「法人化」を検討するタイミングです。個人事業主としての節税には限界がありますが、法人化することでさらに広範な節税策が可能になります。
所得分散で家族に給与を出す
法人化の大きなメリットの一つが、所得を家族に分散できる点です。
- 個人ではできない家族給与の枠拡大: 個人事業主の場合、家族への給与(専従者給与)は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、かつその業務内容や金額が適正であれば経費にできます。しかし、その金額にはある程度の制限や税務上のチェックが入ります。 一方、法人化すると、役員報酬として家族を役員にしたり、従業員として雇用したりすることで、より柔軟に所得を分散できるようになります。
経費計上できる範囲の広がり
法人化すると、個人事業主では難しい、あるいは認められにくい費用も経費として計上できるようになります。
- 役員報酬: 社長であるあなた自身への役員報酬も経費になります。
- 社宅: 法人が所有する物件を、役員であるあなたが社宅として利用することで、家賃の一部を経費にすることができます。
- 車両費: 法人の方が社用車としての利用実態が認められやすく、経費として計上できる範囲が広がる傾向にあります。
- 出張手当: 法人から役員・従業員に支払われる出張手当は、一定のルールに基づけば非課税で受け取ることができ、法人側では経費にできます。
- 生命保険料: 法人契約の生命保険は、契約内容によっては保険料の一部または全額を経費にでき、万一の際には法人が保険金を受け取れます。
法人化で損をしやすいケース
法人化はメリットばかりではありません。規模が小さい段階で法人化すると、かえって税負担や手間が増える可能性があります。
- 小規模のうちは逆に不利になる理由:
- 設立費用: 法人の設立には、登記費用などで20万円〜30万円程度の初期費用がかかります。
- 法人維持コスト: 会社を維持するためには、税理士報酬、社会保険料、法人住民税の均等割(赤字でも年間約7万円程度発生)などの固定費がかかります。
- 社会保険料: 法人の役員になると、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入が義務付けられます。個人事業主で国民健康保険・国民年金に加入している場合と比べて、保険料負担が増えるケースが多いです。
- 会計・税務の複雑化: 個人の確定申告に比べて、法人の会計・税務処理ははるかに複雑になります。
法人化の目安タイミング
法人化の最適なタイミングは、個人の所得や事業規模によって異なりますが、一般的には以下の目安が挙げられます。
- 年間不動産所得(給与所得など他の所得と合算した総所得)が900万円を超える場合: 個人の所得税の最高税率(所得税+住民税で55%)に近づき始める水準です。
- キャッシュフローが潤沢で、かつ経費にできるものが少ない場合: 手元にキャッシュが残っていても、個人事業主として経費にできるものが少ない場合、税金で手取りが減ってしまいます。
- 相続対策を検討し始めた場合: 法人化により、不動産を法人名義にすることで、相続時の評価額を下げるなどの相続税対策に繋がる場合があります。
【重要事項】 法人化の判断は、現在の所得状況、将来の事業拡大計画、家族構成、相続の有無など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。必ず経験豊富な税理士に相談し、複数のシミュレーションを行ってもらった上で、最適なタイミングと形態を決定してください。
ケーススタディ:個人 vs 法人 vs 青色申告
同じ収益でも、税負担がどれだけ変わるか、具体的なシミュレーションで比較してみましょう。
【共通条件】
- 年間の家賃収入:800万円
- 現金支出経費(管理費、修繕費、ローン金利など):300万円
- 減価償却費:200万円
- 個人の給与所得:400万円
- 個人の所得税率:仮に20%(他に控除がないと仮定)、住民税率:10%
- 法人の税率:仮に15%(法人税、所得800万円以下の場合)
3つのパターンでシミュレーション比較
個人事業主(白色申告)
不動産所得: 800万円(収入) − 300万円(現金経費) − 200万円(減価償却費) = 300万円
個人の総所得: 給与所得400万円 + 不動産所得300万円 = 700万円
税金(所得税+住民税): 700万円 × 30% = 210万円 (厳密には累進課税のため、実際の税率はもっと高くなる可能性があります)
個人事業主(青色申告、65万円控除、損益通算)
不動産所得: 800万円(収入) − 300万円(現金経費) − 200万円(減価償却費) = 300万円
青色申告特別控除適用後不動産所得: 300万円 − 65万円 = 235万円
個人の総所得: 給与所得400万円 + 不動産所得235万円 = 635万円
税金(所得税+住民税): 635万円 × 30% = 190.5万円 → 白色申告と比べて約19.5万円の節税
法人(法人化し、あなたが役員報酬を受け取る場合)
法人での利益: 800万円(収入) − 300万円(現金経費) − 200万円(減価償却費) = 300万円
あなたの役員報酬:仮に年間200万円を役員報酬として設定
法人の所得: 300万円(法人利益) − 200万円(役員報酬) = 100万円
法人の税金(法人税など): 100万円 × 15% = 15万円
あなたの個人所得: 給与所得400万円(本業) + 役員報酬200万円 = 600万円
あなたの個人の税金(所得税+住民税): 600万円 × 30% = 180万円
合計税負担(法人税+個人税): 15万円 + 180万円 = 195万円
このシミュレーションでは、青色申告と法人化で税額が大きく変わることが分かります。
法人化のメリットは、家族への給与支給など所得分散の自由度がさらに高まることで、全体の税負担をより最適化できる点にあります。また、法人に残った利益を将来の物件購入資金として積み立てたり、役員退職金として準備したりと戦略的な運用も可能になります。
【重要事項】 上記のシミュレーションは極めて簡略化したものです。実際には、社会保険料、消費税、各種控除、法人住民税均等割、事業税、個人事業税など、考慮すべき要素が多数存在します。 必ず、あなたの現状に即した正確なシミュレーションを税理士に依頼してください。 税理士は、税額だけでなく、社会保険料負担や手続きの手間、将来的な事業計画まで含めて、最適な選択肢を提案してくれます。
節税をやりすぎないための注意点
節税は合法的な範囲で行うべきであり、「節税」と「脱税」の線引きは非常に重要です。
「節税」と「脱税」は紙一重
- 節税: 税法で認められた範囲内で、合理的な方法により税金を減らすこと(例:経費の適正計上、控除の活用、制度の利用)。
- 脱税: 偽装、隠蔽など不正な行為によって、納税義務を不法に免れること(例:架空経費の計上、売上隠し)。
脱税は犯罪であり、発覚すれば追徴課税(重加算税など)や延滞税が課せられるだけでなく、社会的な信用を失い、刑事罰の対象となる可能性もあります。
税務調査で否認されるパターン
特に不動産投資における税務調査では、以下の点に注意が必要です。
- プライベートな支出の経費計上: 「家事按分」が認められる場合もありますが、個人的な飲食代、旅行代、自家用車のガソリン代などを事業経費として全額計上していると、税務調査で指摘されやすいです。 例えば、物件見学と称して旅行に行きその費用を全額経費にするなどはNGです。
- 過剰な修繕費計上: 明らかに物件の価値を高めるような「資本的支出」(減価償却の対象)を、一括で経費にできる「修繕費」として計上している場合も指摘の対象になります。どちらに該当するかは判断が難しいため、都度税理士に相談しましょう。
- 不自然な赤字の継続: 損益通算を目的に、意図的に過度な経費計上や減価償却費の調整を行い、不自然に多額の赤字を長期間計上していると、税務署の調査対象となることがあります。
- 帳簿の不備・証拠不十分: 領収書や請求書がない、帳簿がきちんと作成されていないなど、経費計上の根拠となる資料が不足している場合も経費が否認される原因となります。
税理士の選び方・相談のコツ
不動産投資の税務は専門性が高いため、税理士のサポートは不可欠です。
- 不動産投資に詳しい税理士を選ぶ: 一般的な税理士でも対応は可能ですが、不動産投資の経験が豊富で、最新の税制改正や融資動向にも詳しい税理士を選ぶことを強くお勧めします。賃貸管理や物件選びのアドバイスまでしてくれる税理士もいます。
- セカンドオピニオンも検討: 一人目の税理士の意見だけでなく、複数の税理士に相談してセカンドオピニオンを得ることも有効です。異なる視点からのアドバイスで、より最適な節税策が見つかることもあります。
- 定期的なコミュニケーション: 税理士とは、確定申告の時だけでなく、購入検討時や大規模修繕時、売却時など、常に密に連絡を取り、早めに相談するようにしましょう。事前に相談することで、税務上のリスクを回避し、最適なタイミングで節税策を実行できます。
- 費用は「投資」と考える: 税理士費用は安くありませんが、その費用は「節税効果」や「税務リスクの回避」という形でリターンを生みます。税理士費用を単なるコストではなく、賢い「投資」と捉えましょう。
まとめ|今日からできる節税チェックリスト
不動産投資における節税は、知っているか知らないかで手元に残るキャッシュが大きく変わります。今日からできる節税のチェックリストを確認し賢い経営を目指しましょう。
まず「減価償却」と「青色申告」を確認しよう
現在不動産投資を行っている方は、まずご自身の物件の減価償却費が適切に計上されているか確認しましょう。特に中古物件では、減価償却を多く取れる可能性があります。
青色申告の承認申請を済ませていますか? まだ白色申告の場合は、ぜひ青色申告への切り替えを検討し、最大65万円の控除や損益通算、繰越控除のメリットを享受しましょう。
これらの手続きには期限や要件がありますので、必ず税理士に相談してください。
将来的な「法人化」シミュレーションをしておく
現時点では個人事業主の方が有利でも、将来的に不動産所得が増加したり、他の所得と合算して税率が上がったりするタイミングが来ます。
今のうちからあなたの所得状況を税理士に伝え、将来法人化した際の税負担がどう変わるか、シミュレーションを依頼しておきましょう。最適な法人化のタイミングを把握しておくことで、機会損失を防げます。
定期的な数字の見直しが重要
税法は常に改正されます。また、あなたの収入や物件の収益状況も変化します。
年に一度の確定申告の時期だけでなく、定期的に自身のキャッシュフローと税負担のバランスを見直し、税理士と相談しながら、常に最適な節税策を検討していくことが重要です。
不動産投資は、単に物件を所有するだけでなく、税務の知識を身につけ、賢く運用していくことで、その真価を発揮します。今回の記事が、あなたの不動産投資の節税戦略を考える上での一助となれば幸いです。
岡山の不動産投資なら岡山の不動産エージェントへ
岡山での不動産投資をご検討中の方は、地域密着で豊富な実績を持つ岡山の不動産エージェントにお気軽にご相談ください。
こんな方はぜひご相談ください
- 岡山での物件探しをサポートしてほしい
- 岡山での物件売却をサポートしてほしい
- 投資収支のシミュレーションを詳しく知りたい
- 地域の最新市場動向を教えてほしい
- 融資や税務についてアドバイスが欲しい
- 全国どこでも対応させていただきます
無料相談・お問い合わせ
RE/MAX VALUE
不動産エージェント 大城 廷寛
📞 電話番号: 080-8354-1201
🏢 事務所: 086-434-6006
📧 メール: takahiro.oshiro@remax-agt.net
📋 宅建免許番号:岡山県知事(1)第6225号
お客様の理想を実現する、不動産パートナーとしてお手伝いいたします。
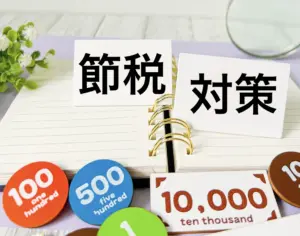


Reviews