「不動産投資に興味はあるけど、いざ物件を買うとなると、何から手をつけていいか分からない…」 「複雑な契約や融資のことが不安で、なかなか一歩を踏み出せない…」
初めての不動産購入は、誰もがこうした不安を抱えるものです。人生で最も高額な買い物の一つである不動産だからこそ、失敗はしたくないという気持ちは当然でしょう。
この不動産投資講座もいよいよ第6回。これまで不動産投資の基礎や物件選び、利回りの見極め方について解説してきました。今回は、いよいよ具体的に物件を「購入する」ステップに焦点を当てます。
- どこで物件情報を探せば良いのか?
- 信頼できる不動産仲介会社の見分け方と付き合い方
- 購入申込から引渡しまでの具体的な流れ
- トラブルを未然に防ぐためのチェックポイント
複雑に思える不動産購入も一つひとつのステップを理解すれば決して難しくありません。さあ、一緒に「初めての不動産購入」への道筋を見ていきましょう。
物件探しはどこから始める?情報収集の「網」を広げる
不動産投資の成功は、良い物件を見つけることから始まります。情報収集の方法は多岐にわたるため、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自身のスタイルに合った方法で「網」を広げることが重要です。
ポータルサイト(楽待、健美家、SUUMOなど)を使う場合
現在、不動産投資を検討する多くの方が最初にアクセスするのが、楽待(らくまち)、健美家(けんびや)、SUUMOなどの大手ポータルサイトです。
メリット
- 手軽さ: 自宅や外出先から、いつでもどこでも大量の物件情報を閲覧できます。
- 情報量: 全国津々浦々の物件が掲載されており、様々な条件で検索が可能です。
- 市場価格の把握: 多くの物件を比較することで、エリアごとの利回り相場や物件価格帯の感覚を掴むのに役立ちます。
- 多様な情報源: 多くの不動産会社が物件を掲載しているため、多様な選択肢から検討できます。
デメリット
- 競争率の高さ: 誰でも見られる公開情報であるため、良い物件はすぐに買い手がついてしまいます。特に高利回り物件や優良物件は、掲載された数時間、あるいは数分で問い合わせが殺到し、すでに売約済みになっていることも珍しくありません。
- 情報鮮度の遅さ:
ポータルサイトに掲載されるまでにはタイムラグがあります。本当に良い物件は、掲載される前に決まってしまうことが多いです。これは、売主が複数の不動産会社に売却を依頼している「一般媒介」の場合に特に顕著で、各社がポータルサイトに掲載する準備をしている間に、既に別のルートで買付が入ることもあります。 - 情報過多による混乱: 物件数が多すぎて、初心者はどれを選べば良いか迷ってしまうこともあります。
- 広告物件の存在: 魅力的に見せるための広告要素が含まれている物件も少なくありません。表面的な情報だけでなく、その裏側にある実態を見抜く力が求められます。
物件情報の見方と注意点
- 表面利回りだけでなく、必ず実質利回りを概算する: 第5回で解説した通り、表面利回りの高さだけで判断せず、固定資産税、管理費、修繕費、空室率などを考慮した実質利回りを必ず自分である程度概算しましょう。
- 写真と図面だけでなく、周辺地図を徹底的に確認する: 最寄駅からの距離、周辺の施設(スーパー、コンビニ、病院、学校)、騒音源(幹線道路、工場)、嫌悪施設(ゴミ処理場、風俗店など)の有無をGoogleマップやストリートビューで徹底的に確認します。ストリートビューでは、物件の入り口やゴミ置き場の状況、電柱の位置などもチェックすると、現地に行った際とのギャップが少なくなります。
- 物件所在地を必ず確認し、ハザードマップもチェックする: 住所が番地まで記載されているか確認し、国土交通省のハザードマップや各自治体の情報を参照し、過去の災害履歴や将来的な災害リスクがないかを必ず確認しましょう。特に浸水想定区域や土砂災害警戒区域は要注意です。
不動産会社(業者)からの紹介
「非公開物件」や「先行情報」を手に入れるには、信頼できる不動産会社とのつながりが不可欠です。
一般媒介と専任媒介の違い
- 一般媒介: 複数の不動産会社が同時に物件の売却を依頼されている状態です。多くの情報源から物件が入手できる可能性がありますが、各社が「売ってあたりまえ」の感覚で、顧客への情報提供の優先順位が低い場合もあります。
- 専任媒介・専属専任媒介: 1社のみが売却を依頼されている状態です。その会社が販売に力を入れるため、顧客(購入検討者)への紹介が優先される傾向があります。本当に良い物件は、ポータルサイトに掲載される前に、この専任媒介の段階で信頼できる顧客に紹介され、そのまま契約に至るケースが非常に多いです。「水面下物件」「未公開物件」と呼ばれる情報の多くがこれに当たります。
自分で見つける vs 紹介を待つ
ポータルサイトで自分で見つけるのは「誰もが見られる情報」なので、競争率が高いです。
不動産会社からの紹介は、彼らが抱えている「非公開情報」や「公開前の先行情報」を得られるチャンスです。優良な物件を手に入れるための最も確実な方法の一つです。信頼関係を築き、あなたの希望条件を明確に伝えることで、優先的に情報をもらえるようになります。担当者との定期的なコミュニケーション(週に一度、月に一度など)が、良い情報を受け取るためのカギとなります。
知人や大家ネットワークからの紹介
最も有力で、かつ競争率の低い情報源の一つが知人や既存の大家ネットワークからの紹介です。
オフレコ情報の強み
「もう不動産投資はやめるから、知り合いに良い物件を譲りたい」「自分の知り合いの大家さんが、物件を手放そうとしているらしい」といった、一般には流通しない「オフレコ情報」が手に入ることがあります。
こうした情報は、売主の事情で急いで売却したいケースも多く、掘り出し物に出会える可能性が非常に高いです。価格交渉もしやすい傾向にあります。
また、物件の過去の修繕履歴や入居者情報、周辺環境の細かい情報など、通常の売買では知り得ない詳細な情報を得られることもあります。
注意すべきリスク
個人間売買になる場合、仲介会社が間に入らないことで、重要事項の説明が不十分になったり、トラブル時の法的保護が薄くなったりする可能性があります。必ず弁護士や司法書士といった専門家を間に挟み、書面での契約を怠らないようにしましょう。
親しい間柄であっても、物件のデメリットを正直に話してくれない可能性もあります。感情的にならず、プロ(別の仲介会社やインスペクター)の目線で冷静に物件評価を行うことが重要です。
仲介会社はどう選ぶ?「長く付き合えるパートナー」を見つけるコツ
不動産購入において、仲介会社選びは物件選びと同じくらい、あるいはそれ以上に重要です。彼らはあなたの物件探しから契約、引渡しまでをサポートしてくれる「パートナー」だからです。
良い仲介会社を見分けるチェックポイント
レスポンス速度と丁寧さ、そして提案力
問い合わせに対する返信が早いか、電話をかけてすぐに繋がるかなど、基本的な連絡の速さは非常に重要です。良い物件情報はスピード勝負だからです。
質問に対する回答が丁寧で分かりやすいか、専門用語を羅列せず、初心者にも理解できるように説明してくれるかどうかも見極めるポイントです。
さらに、あなたの希望条件に対して、ただ物件を送るだけでなく、「この物件は〇〇の理由でおすすめです」「〇〇というリスクがあるので、こう対処しましょう」といった、具体的な提案やリスクヘッジのアドバイスをしてくれるかが、真のプロフェッショナルを見分けるカギとなります。
専門分野(投資用か、地域特化か、そして担当者の個性と引き出し)
「投資家目線」と「入居者目線」の両方を持つ会社・担当者を選びましょう。 不動産投資は、収益を追求する「投資」であると同時に、入居者が「住みたい」と思える魅力的な物件であるかどうかも、空室対策や家賃収入の安定に直結します。
居住用不動産を主に扱う会社や担当者でも、投資物件を扱うことはありますが、彼らの主な視点は「購入者の居住快適性」に偏りがちです。一方で、投資用不動産専門の会社でも収益性ばかりを重視し、入居者のニーズや物件の魅力を軽視するケースもあります。
あなたの不動産投資の目的が「安定的な収益を上げること」である以上、利回り計算、キャッシュフロー最大化、税務、融資戦略、賃貸管理といった投資家特有の専門知識に加え、入居者が長く住みたくなる物件の価値を見抜ける、あるいは高められる「入居者目線」のアドバイスができる担当者を選ぶことが賢明です。
また、あなたが検討しているエリアに特化している会社も有効です。その地域の賃貸相場、空室率、人口動態、競合物件の状況、修繕業者の情報など、肌感覚で詳細な情報を持っている可能性が高いです。
さらに重要なのは、担当者個人の「強み」や「引き出しの多さ」です。担当者の中には、空室対策のアイデアや具体的なリフォーム提案に長けた者、融資に非常に強い者、あるいは老朽化した物件の建て壊しから新築への再活用プランまで描ける者など、それぞれに得意分野があります。あなたの投資目的(例えば、築古を再生したい、高利回りな物件を早期に取得したい、出口戦略を重視したいなど)と合致する強みを持つ担当者を見つけることで、より質の高いサポートが期待できます。
管理や売却まで見てくれるか(ワンストップサービスの真贋)
物件購入後の賃貸管理、そして将来の売却までをワンストップでサポートしてくれる会社だと、長期的なパートナーとして非常に心強いです。購入段階から、将来の出口戦略を見据えたアドバイスをもらえます。
ただし、購入と管理の両方を手掛ける会社は、自社で管理したいがために管理料が高めに設定されていたり、強引な物件紹介をしたりする場合もあるため、複数の会社の意見を聞くなど冷静な判断が必要です。管理会社の評判は、入居者からの口コミサイトや、実際にその管理会社を利用しているオーナーに聞くのが最も確実です。
仲介手数料は「単なるコスト」ではない理由
不動産仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限が定められており、「物件価格の3%+6万円+消費税」が一般的です。例えば5000万円の物件なら約171万円にもなります。決して安くない費用ですが、「単なるコスト」としてケチるのは賢明ではありません。
プロの仕事への正当な対価
良い仲介会社は、物件の選定、価格交渉、融資付けのサポート、契約書の作成・確認、重要事項説明、引渡しまでの膨大な事務処理、そしてその間の見えないリスクヘッジなど、非常に多岐にわたる専門的な業務をこなします。
彼らの労力と知識、そして何よりも「責任」に対する正当な対価なのです。
良い情報へのパスポート
仲介手数料は、不動産会社にとって重要な収益源です。当然、手数料をしっかり払ってくれる、あるいは払ってくれる見込みのある「優良顧客」には、非公開情報や優先的な物件情報が回ってきます。
手数料を値切ることで、担当者のモチベーションが下がり、最悪の場合、あなたを「購入意欲の低い客」と判断し、本当に良い物件が手元に来なくなる可能性もゼロではありません。「目先の手数料を惜しんで、大きな機会を逃す」という事態は避けたいものです。
長く付き合えるパートナー選びの鉄則
言いなりになるのは危険、自分の希望やNGを明確に伝える(本音で語る)
「何でもお任せ」は危険です。自分の投資目的(インカムゲイン重視か、キャピタルゲイン重視か)、予算、希望エリア、リスク許容度、避けたい条件(築年数、構造、再建築不可、特定のリスク物件など)を明確に担当者に伝えましょう。
これに加えて、「どんな物件なら購入を決断しやすいか」「どんな物件は絶対避けたいか」といった、より具体的な好みや判断基準を伝えることで、担当者もあなたに合った物件を探しやすくなります。不明な点や疑問は遠慮なく質問し、納得いくまで説明を求めましょう。「この担当者なら、裏表なく本音で話せる」と感じる相手を見つけることが重要ですし、あなた自身も本音で話せる関係性を築く努力が不可欠です。
複数の仲介会社・担当者と付き合い、比較検討する
初めから1社に絞る必要はありません。複数の仲介会社に登録し、それぞれの担当者と話をすることで、彼らの専門性や対応の質を比較検討できます。
異なる会社から入ってくる情報を比較することで、市場全体の動向や物件の適正価格をより客観的に判断できるようになります。「この物件、他の会社からは紹介されなかったな」という気づきが、担当者の情報収集力や提案力の差を見極めるヒントにもなります。
購入申込(買付)から引渡しまでの流れを徹底解剖
良い物件が見つかり、仲介会社との信頼関係も築けたら、いよいよ購入の具体的なステップに入ります。ここからは、時間軸に沿って流れを追っていきましょう。
1. 買付(購入申込)
買付証明書って何?
購入したい物件が見つかったら、まず「買付証明書(購入申込書)」を売主へ提出します。これは、「この物件を〇〇円で買いたい」という意思表示を公式に行うための書面です。
買付証明書には、購入希望価格、契約希望日、手付金の額、融資利用の有無、引渡し希望日などが記載されます。
法的拘束力はありませんが、買付提出は「本気度」を示すものです。安易な買付は避け、本当に購入したい物件にのみ提出しましょう。
ここで価格交渉も
買付証明書を提出する際に、売主の希望価格よりも低い金額(「指値(さしね)」といいます)を提示して、価格交渉を行うことが一般的です。
仲介会社と相談し、周辺相場、物件の状態(築年数、修繕履歴、設備の古さなど)、売主の事情(急ぎで売りたいか、資金に余裕があるかなど)を総合的に考慮して、妥当で「売主が応じる可能性のある」指値を行いましょう。あまりにかけ離れた指値は、売主の心証を悪くし、交渉が決裂する原因にもなりかねません。売主が指値を受け入れれば、契約へと進みます。
2. 融資審査
不動産投資では、多くの場合、金融機関からの融資を利用します。このプロセスが、購入までの最も長い期間を占めることもあります。
銀行選び、事前審査、本審査
- 銀行選び:
日本政策金融公庫、メガバンク、地方銀行、信用金庫、信用組合、ノンバンクなど、様々な金融機関があります。自身の属性(年収、勤続年数、自己資金、既存の借り入れ状況など)や、購入する物件の種別(アパート、マンション、戸建)、エリア(地銀や信金は地元優先)によって、融資を受けやすい金融機関は大きく異なります。仲介会社は融資に強い金融機関を紹介してくれるはずですが、複数の金融機関に自分で打診することも重要です。 - 事前審査(仮審査): 物件が決まったら、まず金融機関に事前審査を申し込みます。あなたの収入や信用情報などを基に「いくらくらいまで借りられそうか」を判断する簡易的な審査です。通常、数日から1週間程度で結果が出ます。ここで「融資内諾」が出れば、本格的な購入プロセスに進めます。
- 本審査:
事前審査が通ったら、売買契約を締結し、正式な本審査に臨みます。ここでは、あなたの個人情報だけでなく、購入する物件の担保評価(担保として十分な価値があるか)、収益性(家賃収入でローンが返済可能か)なども厳しく審査されます。必要書類も多く、時間もかかるため(数週間〜1ヶ月程度)、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。金利と返済期間は、あなたのキャッシュフローに直結するため、非常に重要です。
金利・返済条件の比較(変動金利と固定金利のリスク)
複数の金融機関で審査を進め、金利、返済期間、担保評価額、手数料などの条件を比較検討しましょう。わずかな金利差でも、長期的な返済額には大きな違いが出ます。
変動金利か固定金利かは、今後の金利動向を見据えた重要な選択です。変動金利は当初の金利が低いメリットがありますが、将来的な金利上昇リスクがあります。固定金利は金利変動リスクを負わない安心感がありますが、当初の金利は高めです。
返済方法(元利均等返済か元金均等返済か)、繰り上げ返済の条件なども確認しておくことが重要です。元金均等返済は、返済当初のキャッシュフローは厳しくなりますが、元金が早く減るため、総支払利息が少なくなるメリットがあります。
3. 契約(売買契約)
融資の内諾が得られたら、いよいよ売主と買主が顔を合わせて、不動産の売買契約を締結します。
重要事項説明(「読み合わせ」はNG!「理解」が必須)
契約に先立ち、宅地建物取引士が「重要事項説明」を行います。これは、物件の権利関係、法令上の制限、代金の支払い方法、引渡し時期、物件の現況、設備、特約条項など、買主が知っておくべき重要事項を説明するものです。
ただ説明を聞くだけでなく、不明な点は必ず質問し、納得いくまで説明を受けましょう。宅地建物取引士は、説明義務はありますが、買主の利益だけを考えているわけではありません。疑問を解消せず「読み合わせ」で済ませてしまうと、後々のトラブルの原因になります。事前に説明書を読み込み、質問事項をリストアップしておくことをお勧めします。
手付金、違約金の内容とその意味
契約時には、通常、物件価格の5%〜10%程度の「手付金」を売主に支払います。これは、契約解除の際にペナルティとなるお金です。
買主からの解除の場合は手付金を放棄し、売主からの解除の場合は手付金の倍額を支払う(手付倍返し)ことで契約を解除できます。
契約書には、契約違反時の「違約金」の規定も記載されています。これは、手付金以上の損害が発生した場合に適用される条項で、通常は物件価格の10%〜20%に設定されます。
特約条項はあなたの「命綱」!プロに相談を
契約書には、通常の取引条件に加えて、個別の「特約条項」が記載されることがあります。
- 融資特約: 「住宅ローンが借りられなかった場合は契約を解除でき、手付金が返還される」という条項。ほとんどのケースで付けられますが、その期限や解除条件を必ず確認しましょう。
- 物件調査特約: 地中に埋設物が見つかった場合、土壌汚染が判明した場合など、特定の状況で契約を解除できる特約。
- 設備の保証期間特約: 中古物件の場合、売主が引き渡し後〇ヶ月間、主要設備(給湯器、エアコンなど)の故障について責任を負う、といった特約。これがなければ、引き渡し後すぐに設備が故障しても自己負担になるため、非常に重要です。
これらの特約は、あなたの権利とリスクを大きく左右する「命綱」です。必ず内容を理解し、必要であれば弁護士などの専門家に相談して、不利な条件がないか、あるいは追加すべき特約がないか確認しましょう。
4. 決済・引渡し
融資の本審査も通り、最終的な準備が整ったら、物件の引渡しと残代金の支払いを同時に行います。これが「決済」です。
決済日の流れ
通常、買主、売主、仲介会社、金融機関の担当者、司法書士が一堂に会して行われます。
買主は金融機関から融資を実行してもらい、その資金で残代金を売主へ支払います。同時に、固定資産税や都市計画税、管理費、修繕積立金などの精算金(日割り計算)も支払います。
司法書士は、残代金の支払いを確認後、法務局で物件の所有権移転登記を申請します。
残代金支払いと所有権移転登記
残代金の支払いを確認後、司法書士が法務局で所有権移転登記を申請します。これにより、物件の所有者があなたに移転します。
登記が完了するまでには数日〜数週間かかりますが、登記申請がなされた時点で法的な所有権は移転します。登記識別情報(昔の権利証)の書類を司法書士から受け取ったら、大切に保管しましょう。
物件の鍵の受け取りと現況確認
残代金の支払いが完了し、所有権移転登記の手続きが始まれば、売主から物件の鍵を受け取ります。これで、晴れてあなたがその不動産のオーナーとなります。
鍵を受け取る際に、必ず売買契約書に記載された「引渡し時の物件の状態」と相違がないか、最終確認を行いましょう。設備表に記載されたものが全て揃っているか、動作に問題がないかなど、細部までチェックします。何か不備があれば、その場で指摘し、仲介会社を通じて売主に対応を求めましょう。
トラブルを避けるための「プロが意識する」チェックポイント
購入ステップを進める上で、特に注意すべきは「後で後悔しないための徹底確認」です。契約前、引渡し前に、プロの視点で徹底的にチェックし、リスクを最小限に抑えましょう。
契約書・重要事項説明の見方(見落としがちな罠と対策)
瑕疵担保免責(現況有姿)の本当の意味と対策:
中古物件の売買では、「瑕疵担保責任免責(現況有姿)」という条項がよく見られます。これは、「売主は、物件の引き渡し後に見つかった隠れた欠陥(瑕疵)について、一切責任を負いません」という意味です。
この条項がある場合、購入後に雨漏りや給排水管の破損、シロアリ被害などの重大な瑕疵が見つかっても、原則として売主に修理費用を請求できません。特に築古物件やDIYされた物件では注意が必要です。
対策:
- ホームインスペクション(建物診断)の実施: 専門家による建物診断を契約前に依頼し、構造上の問題や設備の劣化状況、修繕履歴などを詳細に確認します。費用はかかりますが、後々の高額な修繕費用を考えれば、必要な投資です。
- 価格交渉の材料にする: インスペクションで判明した修繕費用などを根拠に、売主に価格交渉をさらに持ちかけましょう。
- 買主側の保険加入: 既存住宅売買瑕疵保険など、買主側の保険に加入することで、万が一の瑕疵が見つかった際の補償を得ることができます。
設備表・現況確認書の「記載漏れ」に注意
売買契約時には「設備表」と「現況確認書」が添付されます。
設備表には、物件に付属する設備(エアコン、給湯器、コンロなど)の有無、種類、故障の有無、経過年数などが記載されます。引渡し時に記載されたものが揃っているか、正常に作動するかを売主・仲介担当者立ち会いのもと、全て実際に動かして確認しましょう。
現況確認書には、売主が認識している物件の状況(雨漏り、シロアリ被害、隣地との境界紛争、アスベストの使用有無、地中埋設物の有無など)が記載されます。ここに記載がないからといって問題がないとは限りませんが、重要な情報源です。これらの情報は、後にトラブルになった際の証拠にもなるため、一点の曇りもなく、詳細に確認し、不明点は必ず質問しましょう。
引渡し後に後悔しないための「徹底した」最終チェックポイント
引渡し前に、もう一度以下の点を現地で確認し、詳細な写真と動画を残しておきましょう。これは、後に問題が発生した際の重要な証拠となります。
水回り・雨漏り・漏水の兆候
キッチン、浴室、トイレ、洗面台の蛇口をひねって水が出るか、排水はスムーズか。長時間水を流し、目視と聴覚で水漏れの兆兆がないか確認します。特に目に見えない壁の中や床下の配管からの漏水は、後に大きな問題に発展することがあります。
天井や壁に過去の雨染みがないか。特に雨の日の後や、台風の直後など、複数回、異なる天候の日に見に行くと良いでしょう。ベランダの防水層の劣化や、外壁のクラックなども入念にチェックします。
境界問題・越境物
土地の境界線が明確か、隣地との間に塀やフェンスが正しく設置されているか。隣の木の枝や建物の基礎、配管などがあなたの敷地に「越境」していないか、細部まで確認します。
境界標(杭など)があるか確認し、なければ事前に測量図を取得するか、売主負担で測量してもらうよう交渉しましょう。境界問題は、後々の隣人トラブルの最大の原因の一つであり、解決には多大な時間と費用がかかります。
入居者トラブル、管理費滞納(区分マンションの場合)
居住中の物件の場合、入居者の属性(単身、ファミリー、高齢者など)や、過去の家賃滞納歴、近隣住民とのトラブルがないか、管理会社を通じて詳細に確認しましょう。「良い入居者」がいるかどうかが、購入後のキャッシュフローに直結します。
区分マンションの場合、管理費や修繕積立金の滞納がないか、売主に確認を求めましょう。滞納があれば、引渡しまでに精算してもらうのが原則です。管理組合の議事録や修繕計画も確認し、将来の大規模修繕計画や積立金の状況を把握することが重要です。
付帯設備の動作確認と耐用年数
給湯器、エアコン、インターホン、照明器具、シャッターなど、付帯する全ての設備が正常に動作するか、引渡し前に再度確認しましょう。リモコンの有無、電池残量までチェックします。
さらに、これらの設備の設置年数やメーカー保証期間も確認し、おおよその耐用年数を把握しておくことで、将来の交換時期と費用を予測できます。特に給湯器やエアコンは高額な交換費用がかかるため、要チェックです。
まとめ
初めての不動産購入は大きな決断です。この記事で解説したように、ステップごとの流れを理解し、それぞれの段階で必要なチェックポイントを抑えておけば、決して難しいことではありません。
購入ステップは難しくないが、流れを理解しリスクを減らすことが大切
物件探しから引渡しまで、一連の流れを事前に把握し、何に注意すべきかを理解していれば、不要な不安を減らし、冷静な判断を下せるようになります。焦らず、一つひとつのステップを丁寧に進めましょう。特に、契約書や重要事項説明書の内容は、専門家の力を借りてでも徹底的に理解してください。
信頼できる仲介業者を味方につけて進めよう
不動産投資の成功には、良きパートナーとなる仲介業者の存在が不可欠です。あなたの希望を理解し、物件情報だけでなく、融資や税金、管理のアドバイスまでしてくれる、長く付き合えるプロフェッショナルを見つけることが、安心して不動産購入を進めるための最も重要なポイントです。
この記事が、あなたの不動産投資への最初の一歩を力強くサポートすることを願っています。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
岡山の不動産投資なら岡山の不動産エージェントへ
岡山での不動産投資をご検討中の方は、地域密着で豊富な実績を持つ岡山の不動産エージェントにお気軽にご相談ください。
こんな方はぜひご相談ください
- 岡山での物件探しをサポートしてほしい
- 岡山での物件売却をサポートしてほしい
- 投資収支のシミュレーションを詳しく知りたい
- 地域の最新市場動向を教えてほしい
- 融資や税務についてアドバイスが欲しい
- 全国どこでも対応させていただきます
無料相談・お問い合わせ
RE/MAX VALUE
不動産エージェント 大城 廷寛
📞 電話番号: 080-8354-1201
🏢 事務所: 086-434-6006
📧 メール: takahiro.oshiro@remax-agt.net
📋 宅建免許番号:岡山県知事(1)第6225号
お客様の理想を実現する、不動産パートナーとしてお手伝いいたします。

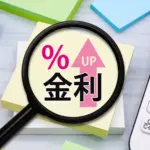

Reviews