なぜあの人は儲かるのか?不動産投資成功の9割は「物件選び」で決まる!
不動産投資で「成功する人」と「そうでない人」の差は、実は物件選びの段階でほとんど決まっている、と言っても過言ではありません。資金計画をしっかり立て、融資の目処が立っても、肝心の物件選びを間違えてしまえば、あなたの描いた夢は絵に描いた餅になってしまいます。
「どんな物件を選べば良いのかわからない」「何に注意して見たら良いの?」と悩む初心者の方も多いでしょう。市場にはたくさんの物件情報が溢れていて、どれが本当に“良い物件”なのかを見抜くのは至難の業に思えるかもしれません。しかし、ご安心ください。不動産投資における「良い物件」を見抜くには、押さえるべき確かな視点があります。
この記事では、あなたが不動産投資で失敗しないために、そして安定した収益を上げ続けるために初心者が特に注視すべき「物件選びの5つの基本視点」を徹底解説します。表面的な情報だけでなくその裏に隠されたリスクやチャンスを見つけるための具体的なチェックポイントまで一つひとつ紐解いていきます。
1. 立地はすべてを凌駕する!絶対に妥協できない「黄金の条件」
不動産投資において、昔から「立地、立地、立地」と言われるほど、立地は最も重要な要素です。一度購入したら動かせない物件にとって立地は賃貸需要、家賃水準、空室リスク、そして将来の売却価格にまで絶大な影響を与えるからです。
物件の良し悪しより「どこにあるか」が成否を分ける理由
運用中の空室リスクに絶大な影響を与える
どんなに内装が綺麗で新しい設備が揃っていても、人が住みたがらない場所に物件があれば、家賃収入は途絶えます。交通の便が悪かったり、周辺に生活施設が乏しかったり、治安が悪かったりするエリアは、空室期間が長引くか、家賃を大幅に下げないと借り手が見つからない事態に陥ります。特に日本では少子高齢化と人口減少が進行しており、地方においてはその傾向が顕著です。エリアの賃貸需要がなければ、物件はただの“箱”と化してしまいます。
売却時の出口戦略に大きく影響する
不動産投資は、最終的には物件を売却して資金を回収し、利益を確定する(キャピタルゲインを得る)ことも視野に入れるべきです。需要のないエリアの物件は、いざ売却しようとしても買い手が見つからず、大幅な値引きを余儀なくされる可能性が高まります。最悪の場合、売却自体が困難になり、負動産と化してしまうリスクさえあります。一方、人口流入が続き、経済が活性化している人気エリアの物件は、賃貸付けがしやすいだけでなく、売却時にも需要が高く、スムーズに、時には購入時よりも高く売却できる可能性を秘めています。
特別の知識よりも「情報の集め方」がカギ
エリア選定には特別な不動産鑑定士のような専門知識は不要です。重要なのは、正確な情報を効率的に集め、客観的に分析する力です。インターネット上の公開情報、自治体の統計データ、現地でのヒアリングなど、多角的に情報を集めることで、そのエリアの本当の姿が見えてきます。表面的な情報だけでなく、その土地に住む人々の暮らしや価値観を想像する「生活者目線」を持つことが良いエリアを見抜く上で非常に有効です。
2. 賃貸需要の見抜き方:地図と数字を味方にする
「人が集まる場所」には賃貸需要があります。しかし、漠然としたイメージだけでなく、具体的な数字と現地情報でその需要を裏付けることが重要です。
人口動態(増加傾向か、安定か)と世帯構成の詳細分析
- 人口推移: 過去10年、可能であれば20年間の人口推移を確認し、増加傾向にあるか、少なくとも極端な減少がないかを確認しましょう。総務省統計局の国勢調査や、各自治体の統計資料(「〇〇市 人口動態」などで検索)で入手できます。将来人口推計も参考に、長期的なトレンドを把握することが大切です。
- 世帯数と世帯構成: 単身世帯が増えているのか(都市部や大学周辺に多い)、核家族世帯が多いのか(郊外に多い)、高齢者世帯が増加しているのかによって、需要のある間取りタイプが変わってきます。例えば、単身世帯の増加はワンルームや1Kの需要、ファミリー世帯の増加は2LDK〜3LDKの需要を示唆します。
- 昼間人口と夜間人口: オフィス街や商業施設が多いエリアは、昼間人口は多いが夜間人口が少ない場合があります。これは賃貸需要が限定的であることを示すため、注意が必要です。
大学・病院・大手工場など、継続的な需要の裏付け(「強い磁力」の存在)
特定の賃貸需要を生み出す「マグネット施設(強力な吸引力を持つ施設)」の存在は非常に重要です。
- 大学: 大規模な大学は、学生や教職員向けの賃貸需要を安定的に生み出します。大学の学部再編や新設、閉鎖の予定がないかなど、長期的な動向もチェックしましょう。
- 大規模病院: 医師、看護師、医療スタッフなどの医療従事者向けの需要に加え、関連する医療産業の集積も期待できます。
- 大手工場・研究所・大規模オフィス街: 転勤族や単身赴任者、従業員向けの安定した需要源です。企業の設備投資計画や雇用計画など、将来の動向も可能な範囲で情報収集しましょう。
- 大規模商業施設・複合施設: これらの施設で働く従業員の需要に加え、施設利用者の利便性向上により周辺の居住ニーズも高まります。新しいショッピングモールやエンターテイメント施設の建設予定もチェックポイントです。
交通利便性と周辺環境の詳細な評価
- 駅からの距離: 大都市圏では、駅徒歩5分以内が最も理想的で、10分以内が許容範囲とされます。15分を超えるとよほど他の魅力がない限り入居付けは困難になります。
- 複数路線・駅の利用可否: 複数の路線が利用できる駅や、複数の駅が徒歩圏内にある物件は、交通の選択肢が広がるため、入居者にとって非常に魅力的です。災害時やトラブル時にも代替ルートがある安心感も大きいです。
- バス便の質: 駅からの距離がある場合でも、バス停が近く、主要駅まで1本でアクセスでき運行本数が多い(特に朝晩のラッシュ時)、終バスの時間が遅いなどの条件を満たせば、十分に需要が見込めます。バス停から物件までの道のりの安全性(街灯の有無など)も確認しましょう。
- 生活インフラの充実度: スーパー、コンビニ、ドラッグストア、病院、銀行、郵便局、役所などの生活に必要な施設が充実しているか。徒歩圏内にあると入居者に選ばれやすくなります。特に、スーパーの種類(高級スーパー、激安スーパーなど)や営業時間帯も、ターゲット層のニーズに合致しているかを判断する材料になります。
- 学校区: ファミリー層をターゲットにするなら、評判の良い保育園・幼稚園、小中学校、高校の有無は非常に重要な要素です。学区の評判は、地域の不動産会社や子育て情報サイトで確認できます。
家賃相場と空室率の徹底調査(SUUMO・LIFULL HOME’Sなど活用)
物件選びの際に、必ず自身で「家賃査定」を行いましょう。
- 大手賃貸ポータルサイトの活用: SUUMO、LIFULL HOME’S、アットホームなどの大手賃貸ポータルサイトで、検討物件の周辺エリアにある類似物件(間取り、築年数、広さ、設備などが近いもの)の家賃を調べて比較します。同時に「募集中」の物件数とその掲載期間も確認し入居付けの難易度を推測します。
- 過去の賃貸事例の確認: 不動産会社に依頼して、過去にその物件や類似物件でどのような賃貸実績があったか(レントロール)を確認します。家賃滞納や短期での退去が頻繁に発生していないかなどもチェックしましょう。
- 管理会社へのヒアリング: 複数の地元の管理会社に、そのエリアの具体的な空室率、平均空室期間、入居付けの状況、入居者の属性、人気設備などについてヒアリングすると、よりリアルな情報が得られます。この情報は、事業計画の収支シミュレーションに非常に役立ちます。
3. 利回りだけに惑わされない!実需とのバランスをとる視点
不動産投資の物件情報で、まず目を引くのが「利回り」ではないでしょうか。高利回りの物件は魅力的に映りますが、それだけで判断するのは非常に危険です。
高利回り=高リスク?そのカラクリを理解する
一般的に、利回りが高い物件は何らかのリスクを抱えている可能性が高いことを示唆します。
- 低価格ゆえの高利回り: 地方や築古物件は、物件価格が安いため表面利回りが高く見えがちです。しかし、これが高い空室リスク、高額な修繕費用、あるいは低い担保評価に直結している場合があります。
- 不適切な家賃設定: 見た目の利回りを高く見せるために、相場より高い家賃で設定されているケースも散見されます。この場合、実際の入居付けは極めて困難になり、結果的に家賃を大幅に下げるか、長期間空室となることになり、当初の利回りは絵に描いた餅となります。
- 運営費用の軽視: 表面利回りだけ見ていると、管理費、修繕積立金、固定資産税、火災保険料、共用部電気代、清掃費用など、毎月、毎年かかる「運営費用」が完全に抜け落ちています。これらの費用は意外と大きく高利回り物件でも手元に残るお金はほとんどないという事態になりかねません。
表面利回り vs 実質利回りを正しく読む
表面利回り(グロス利回り)
$$ 表面利回り = \frac{年間家賃収入}{物件価格} \times 100\% $$
物件情報に記載されていることが多く、購入価格に対する家賃収入の割合を示すシンプルな指標です。手軽に比較できるため、物件検索の入り口としては有効ですがこれだけで判断してはいけません。
実質利回り(ネット利回り)
$$ 実質利回り = \frac{年間家賃収入 – 年間運営費用}{物件価格 + 購入諸費用} \times 100\% $$
家賃収入から管理費、修繕費、固定資産税などの年間運営費用を差し引き、さらに購入にかかった諸費用も考慮に入れた、より実態に近い利回りです。この数値で比較検討することが、物件の真の収益力を把握するために非常に重要です。金融機関もこの実質利回りや、DSCR(借入償還余裕率)を重視して融資判断を行います。
「数字以上に、安定稼働できるか」が長期戦で効く
不動産投資は長期戦です。一時的に高い利回りが出てもすぐに空室になったり、高額な修繕費が発生したりしては意味がありません。
- 安定稼働の重要性: 利回りが多少低くても、常に満室に近い状態で安定稼働できる物件の方が、長期的に見て収益は安定します。空室期間が短いということは、賃貸需要が堅固であり、物件の魅力が維持されている証拠です。
- 「損益分岐点」の意識: 家賃がいくらまで下がったら赤字になるのか、何ヶ月空室が続いたら危険なのか、といった「損益分岐点」を事前に把握しておくことが重要です。万一の事態に備え、手元に十分な運転資金(予備費)を確保することも、安定経営の秘訣です。
- 出口戦略との連動: 安定稼働している物件は、賃貸需要の高さが証明されているため、いざ売却する際も買い手が見つかりやすく、適正な価格で売却できる可能性が高まります。
4. 失敗の典型パターン:「高利回りエリア」に潜む落とし穴
特に初心者が陥りやすいのが「高利回り」という言葉に釣られて、リスクの高い物件を選んでしまうパターンです。一見お得に見える物件には必ずその理由があります。
一見お得な「築古・地方・高利回り」に潜む具体的リスク
入居付けの難しさの深掘り
過疎化が進む地方エリアや、老朽化が著しい物件は、家賃を大幅に下げても入居者がなかなか見つからないことがあります。都市部と比較して、若年層の流入が少ない、働き口が限られている、地域のコミュニティが閉鎖的である、公共交通機関が不便であるなど、根本的な賃貸需要が低いことが原因です。一度空室になると、数ヶ月から1年以上にわたって埋まらない「長期空室」のリスクが高まります。これは精神的にも資金的にも大きな負担です。
修繕費の重みと見落としがちな維持費用
築年数の古い物件は、購入価格が安い代わりに、外壁のクラック(ひび割れ)、屋根の防水劣化、給排水管の錆や漏水、共用部分の老朽化、エレベーターのメンテナンス費用など、大規模な修繕が必要となる時期が迫っている可能性が高いです。購入後に想定外の多額の修繕費が発生し、キャッシュフローを大きく圧迫することがあります。事前に専門家による建物診断(ホームインスペクション)の実施や、過去の修繕履歴、長期修繕計画、修繕積立金(区分マンションの場合)の徹底的な確認が不可欠です。また、維持費用には、清掃費、消耗品費、火災報知器点検費用なども含まれ、これらも年間の支出として考慮する必要があります。
管理の手間・入居者層の違いも意外な盲点
管理会社の質と費用
地方では、物件の管理を委託できる地元の管理会社の数が少なかったり、サービスの質にばらつきがあったりする場合があります。実績が乏しい管理会社に依頼すると、入居者対応や空室対策が不十分で、かえってトラブルが増えるリスクも。また、管理委託手数料が都市部よりも割高なケースもあります。
入居者層の特性とリスク
地方の高利回り物件には、生活保護受給者、外国人労働者、あるいは特定業種の従業員など、入居者層が限定される場合があります。家賃滞納のリスクや文化・生活習慣の違いによる近隣トラブル、ゴミ出しルールの問題などが発生する可能性も考慮し、管理体制や入居審査基準を十分に検討する必要があります。
特定施設への依存リスク(工場・大学移転など)
地方都市や郊外の物件で特に注意すべきなのが、特定の施設(工場、大学、大規模病院など)の存在に賃貸需要が大きく依存しているケースです。
- 工場閉鎖・移転リスク
地域経済を支える主要工場が閉鎖されたり、他地域へ移転したりすると、それに伴う従業員の転出により一気に賃貸需要が激減する可能性があります。これは、そのエリア全体の人口減少や経済の停滞にも繋がりかねません。 - 大学の移転・統廃合リスク
学生街の物件の場合、大学のキャンパスが移転したり、複数の大学が統廃合されたりすると、学生の数が激減し、空室が大量発生するリスクがあります。
これらのリスクは、事前に企業のIR情報や大学の発表、自治体の都市計画などを確認することで、ある程度予測できる場合があります。特定の施設に依存しすぎているエリアは慎重な検討が必要です。
5. 全国地方都市で見るエリア選定のヒント
地方都市での不動産投資は、都市部とは異なる視点が必要です。人口が緩やかに減少している地域でも、戦略次第で安定した賃貸経営は可能です。
地方中核都市(例:仙台・新潟・静岡・広島・福岡など)の傾向と戦略
これらの都市は、地方の中でも比較的規模が大きく、人口が集中し、経済活動も活発です。
- 人口の流入がある: 県庁所在地や政令指定都市は、周辺地域からの人口流入があり、都市部ほどではないにせよ、一定の賃貸需要が期待できます。大学や企業の集積がこの流入を支えていることが多いです。
- 交通インフラの充実: 新幹線駅や主要空港、高速道路インターチェンジがあり、公共交通機関もある程度整備されているため、都市機能を維持しやすいです。これにより、ビジネスや観光の拠点としての魅力も高まります。
- 安定した賃貸需要: 大学、大規模病院、企業の支社、官公庁などが集積しており、学生、単身赴任者、転勤族、医療従事者、公務員などの安定した需要が見込めます。これらの施設周辺は、需要の変動リスクが比較的低いと言えます。
人口が緩やかに減る中でも「局所的に需要があるエリア」とは
全体として人口が減少傾向にある地域でも特定の要因によって局所的に賃貸需要が維持されている、あるいは増加しているエリアが存在します。
- 特定の駅周辺: 都市の中心駅や、主要な乗換駅周辺は、多少人口が減っていても、その利便性からくる需要が維持されやすいです。鉄道沿線に限定せず、バス便の利便性が高い地域も検討範囲になります。
- 大規模大学・病院の周辺: 大学の学部再編や新設、病院の増改築などがあれば、新たな需要が生まれる可能性があります。学生や医療従事者のニーズに特化した物件(例:オートロック、独立洗面台、ネット無料など)であれば、競争力を高められます。
- 大型商業施設やアウトレット周辺: これらの施設で働く従業員の需要に加え、利便性向上により周辺の居住ニーズも生まれます。休日の集客力も高く、街の活性化に貢献しているかどうかも着目点です。
- 工業団地・大規模工場の周辺: 地方で安定した雇用を生み出す工場周辺は、従業員の社宅需要や、協力会社からの長期滞在者向け需要などが見込めます。企業の求人動向や、地域の経済ニュースを追うことで将来性を測ることができます。
ファミリー向け/単身向けなど、地域ごとに強い間取りタイプ
- 都心部・駅近: ワンルーム、1K、1LDKなどのコンパクトな単身者向け物件の需要が高い傾向にあります。特に、職住近接を求めるビジネスパーソンや都心で学ぶ学生がターゲットです。
- 地方郊外: 駐車場付きの2LDK、3LDKなど、ファミリー層向けの物件の需要が高い傾向にあります。車社会である地域特性を考慮し、最低1台できれば2台分の駐車スペースが確保できる物件は入居付けに有利です。
- 学生街: バストイレ別、独立洗面台、室内洗濯機置き場、インターネット無料など、学生が重視する設備を備えたワンルーム・1Kが人気です。大学のキャンパスまでの距離や周辺の飲食店・娯楽施設の有無も重要です。
地域によって異なる「戸建賃貸・アパート・区分」の優位性
- 都市部(特に東京23区): 土地の価格が高く、区分マンションが投資の中心となります。高層マンションの需要も高く、高層階や眺望の良い部屋は高値で取引されます。
- 地方中核都市: 区分マンション、アパート、戸建賃貸の全てが選択肢に入ります。駅近であれば区分マンションやアパート、駅から少し離れた郊外では駐車場付きのアパートや戸建賃貸が好まれる傾向があります。
- 地方郊外・過疎地域: アパートや戸建賃貸が中心になりますが、空室リスクや売却時の流動性に細心の注意が必要です。戸建賃貸は、ファミリー層に人気で一度入居すると長期入居になる傾向があるため、安定収入に繋がりやすいですが、数が少ないため物件探しが難しいこともあります。
投資家が注目する地方エリアの共通点(再開発・大学・観光需要など)
- 大規模再開発計画: 駅前広場の整備、商業施設の誘致、タワーマンション建設、公園整備など、自治体主導の大規模な再開発計画があるエリアは、将来的な価値向上が期待できます。自治体の都市計画情報や開発事業者のIR情報をチェックしましょう。
- 観光需要: 観光客が多く訪れる地域では、短期賃貸(民泊など)の需要も考慮に入れることができますが、国の旅館業法や各自治体の条例による規制状況の確認が必須です。通常の賃貸と比べて運営の手間やリスクが異なります。
- 大規模大学の新設・移転: 新しい大学が設立されたり、既存の大学が都心から移転してくる場合、学生や教職員向けの新たな賃貸需要が生まれます。
- 企業の誘致・工場新設: 大手企業の進出や工場新設は、雇用を生み出し、転勤族や従業員の賃貸需要を喚起します。自治体の企業誘致担当部署の発表などにも注目しましょう。
6. 地図に出ないリスクを見抜く目
賃貸需要や利回りといった数字だけでは見えない、物件が抱える潜在的なリスクも存在します。これらは現地調査や周辺住民とのコミュニケーションによってしか得られない「地図に出ない情報」です。
ハザードマップ・浸水想定エリアの徹底確認
国土交通省や各自治体が公開しているハザードマップ(洪水、土砂災害、津波、高潮など)を必ず確認しましょう。物件が浸水想定区域や土砂災害警戒区域に該当していないかを確認します。特に、近年多発するゲリラ豪雨や集中豪雨による内水氾濫リスクも考慮が必要です。
リスクが高いエリアであれば、火災保険・地震保険料が高くなったり、入居者付けが難しくなったりするだけでなく、万一の災害時には物件が大きな被害を受け、復旧に多額の費用と時間がかかり、賃料収入が途絶える可能性もあります。
学区・治安・生活利便性・ゴミ問題など住民視点も大事
- 学区の評判: ファミリー層をターゲットにするなら、評判の良い小中学校区であるかは非常に重要です。地域の不動産会社や、地域の住民コミュニティサイト、子育て情報サイトなどで、学校の評判やPTA活動の活発さを確認できます。
- 治安の詳細確認: 警察署のウェブサイトで犯罪発生率データを確認するだけでなく、昼と夜、平日と週末など、異なる時間帯に実際に物件周辺を歩いて、街の雰囲気や人の流れ、街灯の有無、不審者の有無などを体感しましょう。夜間の人通りの少なさや、繁華街の騒音が響かないかなども確認が必要です。
- 生活利便性と周辺の異臭・騒音源: 騒音源(幹線道路、鉄道、工場、学校や公園での騒音など)、異臭源(工場、畜産施設、ごみ処理場、下水処理場など)、日当たり、風通しなども、現地でしか分からない情報です。特に、幹線道路沿いの物件は、排気ガスや粉塵による汚れ、振動なども考慮に入れるべきです。
- ゴミ問題と周辺環境の清潔さ: ゴミ捨て場の管理状況が悪い物件や、路上にゴミが散乱しているエリアは、入居者トラブルの原因になったり、住環境としての魅力を損ねたりすることがあります。地域の清掃活動や、住民のモラルを推し量る指標にもなります。
SNSや現地調査での“空気感”チェックの勧め
- SNS検索の活用: X(旧Twitter)やInstagramなどで、物件のある地名や駅名、地元のイベント名などで検索してみましょう。住民の生の声や、その地域のポジティブ・ネガティブな情報が見つかることがあります。特に、地域住民が発信する情報は、公式情報では知り得ないリアルな「空気感」を教えてくれます。
- 徹底的な現地調査: 可能な限り、ご自身で複数回(昼夜、平日休日)現地を訪れて、周辺環境を肌で感じることが最も重要です。
- 最寄り駅からの道のり、電車の混雑状況、周辺店舗の活気。
- 物件の管理状況(共用部の清掃状況、ゴミ捨て場、駐輪場、郵便受けなど、細かい部分までチェック)。
- 周辺住民の層や雰囲気(高齢者が多いのか、若い世代が多いのかなど)。
- 夜間の街灯の明るさや人通りの少なさ、騒音レベル。
- 周辺に空き家が目立たないか、地域全体に活気があるか。
- 地元の不動産会社へのヒアリング: 複数の地元の不動産会社を訪れ、そのエリアの賃貸需要、入居者層、空室状況、人気設備、管理の難しさ、トラブル事例などについてヒアリングすると、よりリアルな情報が得られます。地元の情報に精通しているか、誠実に対応してくれるかなども見極めましょう。
7. まとめ:住みやすさを想像する力が、不動産投資の基本
不動産投資における「良い物件」とは、単純に利回りが高い物件ではありません。それは「入居者が長く住み続けたいと思える、そして将来も需要が見込める物件」です。
自分が「住みたいと思えるか」で判断すると失敗しにくい
最終的に、ご自身がその物件に住みたいと思えるか、友人や家族に自信を持って勧められるか、という「住みやすさ」の視点を持って判断することは、失敗を防ぐための重要な感覚です。これは感情論ではなく、先に述べた具体的なチェックポイントをクリアした上で、最終的な「生活者としての心地よさ」を測る感覚です。入居者の目線に立つことで、物件の真の価値が見えてきます。
利回りよりも、安定稼働・出口・修繕リスクの3点を意識
高すぎる利回りに惑わされず、以下の3つの要素を特に重視して物件を選びましょう。
- 安定稼働: 長期間、高稼働率で家賃収入が得られるか。そのエリアの賃貸需要がどれだけ堅固か、競合物件との差別化はできているかを冷静に判断します。
- 出口戦略: いざという時に、スムーズに売却できる流動性があるか。将来の人口減少や市場の変化を見据え、需要が継続するエリアを選定することが重要です。
- 修繕リスク: 想定外の多額な修繕費用がかかるリスクは低いか、事前に把握できているか。特に築古物件では、綿密な調査と修繕計画が不可欠です。
無理に“穴場”を狙わず、「ほどよい選択」が成功に近づく
初心者のうちは、無理に「超高利回りの穴場物件」を探す必要はありません。なぜなら、そういった物件には必ずそれなりのリスクが隠されているからです。むしろ、堅実に安定した収益を目指すのであれば、需要がしっかりあり、価格も適正な「ほどよい選択」をする方が、リスクを抑え、長期的な成功に繋がりやすいでしょう。まずは小さく始めて、経験と知識を積み重ねていくことが、不動産投資の王道です。
この記事が、あなたの不動産投資における「物件選び」の羅針盤となり、賢明な判断を下すための一助となれば幸いです。これから投資を始める方のヒントになれば嬉しいです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
岡山の不動産投資なら岡山の不動産エージェントへ
岡山での不動産投資をご検討中の方は、地域密着で豊富な実績を持つ岡山の不動産エージェントにお気軽にご相談ください。
こんな方はぜひご相談ください
- 岡山での物件探しをサポートしてほしい
- 岡山での物件売却をサポートしてほしい
- 投資収支のシミュレーションを詳しく知りたい
- 地域の最新市場動向を教えてほしい
- 融資や税務についてアドバイスが欲しい
- 全国どこでも対応させていただきます
無料相談・お問い合わせ
RE/MAX VALUE
不動産エージェント 大城 廷寛
📞 電話番号: 080-8354-1201
🏢 事務所: 086-434-6006
📧 メール: takahiro.oshiro@remax-agt.net
📋 宅建免許番号:岡山県知事(1)第6225号
お客様の理想を実現する、不動産パートナーとしてお手伝いいたします。


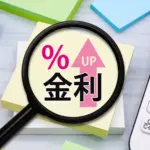
Reviews