不動産投資の世界へようこそ。あなたが物件情報を探し始めると、必ずと言っていいほど目に飛び込んでくるのが「利回り」という数字でしょう。
「なぜ『利回り』を重視するのか?」
それは、利回りが投資額に対してどれくらいの家賃収入が得られるかを示す、収益性の最も分かりやすい指標だからです。この数字が高ければ高いほど、「この物件は儲かりそうだ!」と胸が高鳴るかもしれません。
しかし、ちょっと待ってください。その「利回り」、本当にあなたが手にする儲けを示している数字ですか?
残念ながら、多くの不動産広告に記載されている「表面利回り」だけを鵜呑みにすると、思わぬ落とし穴にはまり、最終的に手元にお金が残らない、いわゆる「赤字物件」を掴んでしまう投資家は後を絶ちません。本には載っているようで、実は深くは語られない、この利回りの「罠」こそが、不動産投資の明暗を分ける最大のポイントなのです。
この記事では、表面的な数字に惑わされず、あなたが確実に利益を出し、長期的に成功するための「生きた知識」を身につけていきましょう。
表面利回り(グロス利回り)の甘い誘惑
まずは、あなたが不動産情報サイトやチラシを見た時に、一番最初に目にする「表面利回り」から見ていきましょう。
不動産広告の「顔」となる数字
物件価格の横に大きく表示されているのが、この「表面利回り(グロス利回り)」です。これは、その物件が満室になったと仮定した場合、年間でどれくらいの家賃収入を生み出すかを、購入価格に対してざっくりと示したものです。
表面利回りの計算式
計算式は非常にシンプルです。
表面利回り=物件購入価格年間満室想定家賃収入×100%
例えば、家賃10万円の部屋が10室あるアパート(満室想定家賃収入100万円/月 = 年間1200万円)を、1億2000万円で購入した場合、表面利回りは以下のようになります。
表面利回り=12000万円1200万円×100%=10%
高い表面利回りの裏に隠された「見えないコスト」
この「10%」という数字だけを見ると、「すごい!年に1割も返ってくるなんて素晴らしい!」と感じるかもしれません。しかし、これはあくまで家賃収入の額面に過ぎず、投資家が手元に得る利益とは大きくかけ離れた数字です。
表面利回りが高い物件は、特に地方や築年数の古い物件に多く見られます。これは、物件価格が安いために相対的に利回りが高く見えるカラクリです。しかし、これらの物件には高利回りの裏に、必ずと言っていいほど「見えないコスト」や「潜在的なリスク」が隠されています。
例えば、
- 物件の維持管理に必要な費用(管理委託費、清掃費、修繕費など)
- 毎年発生する税金(固定資産税、都市計画税)
- 保険料(火災保険、地震保険)
- そして最も恐ろしい「空室期間」による家賃収入の喪失
これらのコストが一切考慮されていないのが表面利回りなのです。表面利回りだけを見て投資することは、まるで美しいパッケージの中身が空っぽかもしれない商品を見た目だけで買ってしまようなもの。不動産投資は、一見華やかに見えても、実態は地道なコスト管理とリスクヘッジが命なのです。
実質利回り(ネット利回り)で「本当の収益力」を見抜く
表面利回りの甘い誘惑から抜け出し、「本当に儲かるかどうか」を見極めるには、「実質利回り(ネット利回り)」を計算することが不可欠です。
広告に載らない「実際の手取り」を可視化する
実質利回りは、単に家賃収入だけでなく、その物件を所有・運営するためにかかる年間費用をすべて差し引いた上で計算される利回りです。これにより、物件から実際にどれくらいのお金が残るのか、よりリアルな収益力を把握することができます。プロの投資家が投資判断の際に最も重視する数字が、この実質利回り、あるいはそれに近い概念であるキャッシュフローです。
実質利回りの計算式
実質利回りの計算式は、以下のようになります。
実質利回り=物件購入価格年間総収入−年間運営費用×100%
ここで重要なのは、分母に「物件購入価格」のみを用いている点です。前回の「物件選びの基本」で解説したように、仲介手数料や登記費用といった購入時諸費用は、あくまで購入時に一度だけ発生する費用であり、毎年の収益性を測る利回りの分母に入れると、物件本来の「収益力」を正確に示せなくなる可能性があります。購入諸費用は、後述するキャッシュフロー計算で自己資金の計算に含める形で適切に考慮します。
「年間総収入」には、単に基本家賃だけでなく、共益費、駐車場代、駐輪場代、自動販売機設置料、更新料(毎年発生する金額を平均化)など、物件から得られる全ての収入を含めて考えます。 「年間運営費用」については、次の項目でさらに詳しく掘り下げていきます。
表面利回りと実質利回りの違いのイメージ
表面利回りは、まるで会社全体の「売上高」のようなものです。たくさんの売上があっても、仕入れや経費が多ければ利益は残りません。
実質利回りは、その売上から原価や運営費を差し引いた後の「営業利益」に近いイメージです。これを見なければ、その事業が本当に儲かっているかは判断できません。
この図式を理解すれば、表面利回りだけで投資することの危険性が、より明確になるでしょう。
利回りを劇的に下げる「隠れた費用」を徹底的に洗い出す
実質利回りを正確に計算するために、広告には記載されない、しかし確実に発生する「年間運営費用」を徹底的にリストアップし、漏れなく計上することが不可欠です。これらの費用は、あなたの手元に残るキャッシュフローを大きく左右します。
管理委託費
多くの場合、不動産会社に賃貸管理を委託する費用です。
- 相場: 一般的に家賃収入の3%〜8%程度。地方ほど割高になる傾向があります。
- チェックポイント
- 管理委託業務の範囲(入居者募集、家賃回収、クレーム対応、修繕手配など)を細かく確認しましょう。
- 家賃保証型のサブリース契約は、一見リスクがないように見えますが、手数料が非常に高く、家賃設定の自由度も低いため、実質利回りが大幅に低下するだけでなく、将来的な家賃減額リスクも考慮が必要です。
修繕費・修繕積立金
物件の維持管理に欠かせない費用です。
- 区分マンションの場合: 毎月「修繕積立金」として徴収されます。
- 注意点: 積立金が適切に設定されているか、長期修繕計画が作成・開示されているかを確認しましょう。積立金が不足している場合、将来的に一時金徴収(追加徴収)が発生する可能性があります。特に築年数の古いマンションでは、大規模修繕を控え、積立金が大幅に値上げされるケースも多いため、必ず管理会社や管理組合に確認が必要です。
- 一棟アパート・戸建の場合: 原則としてオーナーが自身で費用を積み立てていく必要があります。
- 相場観: 一般的に、年間家賃収入の5%〜10%程度を修繕費として計上するのが目安と言われますが、築年数や構造によって大きく異なります。
- 具体的な費用例
- 突発的な修繕: 給湯器故障、エアコン故障、水漏れ、雨漏り、網戸破れなど(数万円〜数十万円)
- 計画的な修繕: 外壁塗装(10〜15年周期で数百万円)、屋上防水(10〜15年周期で数百万円)、給排水管の交換(20〜30年周期で数百万円〜千万円超)、共用部分の照明交換、植栽の手入れなど。
- ホームインスペクション(建物診断): 築古物件の場合、購入前に専門家による建物診断を依頼し、今後発生しうる修繕箇所や費用を洗い出すことを強くお勧めします。これは目先の出費ではなく、将来の大きな損失を防ぐための「保険」です。
固定資産税・都市計画税
毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課される税金です。
- 納税時期: 通常は年4回に分けて納税します。
- 確認方法: 前所有者の納税通知書を見せてもらうか、自治体の窓口で物件の評価額を確認して概算を算出できます。税率は地域によって多少異なりますが、基本的には固定資産税が課税標準額の1.4%、都市計画税が0.3%が目安です。
火災保険・地震保険
万が一の災害に備えるための保険です。
- 必須の費用: ローンを組む場合、火災保険の加入は必須です。地震保険は任意ですが、地震大国日本では加入を強く推奨します。
- 相場: 物件の構造(木造、鉄骨造、RC造など)、所在地、補償内容、期間によって大きく異なります。地震保険は加入期間が長いほど割引が適用される場合もあります。
- チェックポイント: 補償範囲(水災、風災、盗難など)、免責金額、家賃保証特約の有無なども確認し、費用対効果を検討しましょう。
空室損失(稼働率で調整)
最も見落とされがちであり、かつキャッシュフローに大きな影響を与える費用です。どんなに人気エリアの物件でも、退去が発生すれば次の入居者が決まるまで「空室期間」が発生します。この期間は家賃収入がゼロになるため、実質利回りを計算する際には、稼働率(入居率)を現実的に見積もって考慮に入れる必要があります。
- 具体的な見積もり方
- 新築物件でも、退去は必ず発生します。最初の入居者募集期間を考慮し、初年度は90%〜95%、その後は95%〜98%など、物件の特性やエリアの需給バランスに応じて現実的な稼働率を設定しましょう。
- 築古物件や競争が激しいエリアでは、稼働率を80%以下で見ることも必要です。
- 周辺の類似物件の空室状況(SUUMOやLIFULL HOME’Sで「募集中」の物件数とその掲載期間を見る)や、地元の管理会社へのヒアリングが非常に有効です。
入退去費用(原状回復・広告料など)
入居者が退去し、新たな入居者を募集する際に発生する費用です。
- 原状回復費用: 退去した部屋を次の入居者が快適に住めるようにするためのクリーニングや修繕費用です。通常、入居者の過失による損傷は入居者負担ですが、経年劣化による壁紙や床の張替え、ハウスクリーニングなどはオーナー負担となる場合が多いです。
- 広告料(AD: Advertising): 不動産会社が賃貸仲介のために受け取る報酬です。家賃の0.5ヶ月分〜2ヶ月分などと設定されることが多く、空室が長引くほど入居者を見つけるために高額になる傾向があります。
- リフォーム・リノベーション費用: 築古物件の場合、入居付けのために部分的なリフォームや、時には全面的リノベーションが必要になることもあります。これは初期費用の一部とも言えますが、長期的な視点で見れば、入退去時に発生する費用として計上すべきでしょう。
これらの費用は毎年のように発生するわけではありませんが、長期的な運営を考えると年間の平均費用として計上しておくべきです。例えば、5年に一度、50万円のリフォームが発生するなら、年間10万円として計上します。
超実践シミュレーション:表面利回り10%でも「手残りがゼロ」になるカラクリ
具体的な数字を使って、表面利回りだけで判断する危険性、そして実質利回り・キャッシュフローまで見ていくことの重要性を、より実践的にシミュレーションしてみましょう。ここでは、最も重要な「年間キャッシュフロー」に焦点を当てます。
表面利回り10%の物件A
- 物件購入価格: 5,000万円
- 年間満室想定家賃収入: 500万円(月額約41.6万円)
- 表面利回り: 500万円 ÷ 5000万円 = 10%
この数字だけ見ると、非常に魅力的に映るかもしれません。ここに先ほどリストアップした「年間運営費用」を加えて、年間運営収入(NOI: Net Operating Income)を算出します。
年間運営費用(想定)
- 管理委託費(家賃収入の5%):500万円 × 0.05 = 25万円
- 修繕積立金(アパートとして年間積立想定):20万円
- 固定資産税・都市計画税:30万円
- 火災保険・地震保険料:5万円
- 空室損失(稼働率95%と仮定):500万円 × 0.05 = 25万円
- 入退去費用・原状回復費(年間平均):15万円
- その他(共用部電気代、清掃費、消耗品費など):10万円
年間運営費用合計: 25 + 20 + 30 + 5 + 25 + 15 + 10 = 130万円
年間運営収入(NOI)の算出 500万円(年間満室想定家賃収入) – 130万円(年間運営費用) = 370万円
物件単体の実質的な収益力であるNOI利回りも計算してみましょう。 NOI利回り = 370万円 ÷ 5000万円 × 100% = 7.4% 表面利回り10%だったものが、運営費用を引くと実質的な収益力は7.4%まで下がりました。
借入金返済後の「手残り」キャッシュフローを計算する
不動産投資で本当に重要なのは、手元に残る「現金」、つまりキャッシュフローです。特に、ローンを組む場合は、このキャッシュフローがプラスでなければ、毎月持ち出しが発生し、事業継続が困難になります。
仮に、5000万円の物件に対し、自己資金1000万円、借入金4000万円(金利2%、返済期間30年、元利均等返済)で購入したとします。
- 年間ローン返済額: 約176.4万円(月額約14.7万円)
税引前キャッシュフローの算出
370万円(年間運営収入NOI) – 176.4万円(年間ローン返済額) = 193.6万円
さらに「税金」がキャッシュフローを圧迫する
不動産所得は個人の総合所得に合算され、所得税・住民税が課されます。減価償却費などの計上によって課税所得を圧縮することは可能ですが、ここでは簡潔にローン返済後のキャッシュフローに対して税率20%(実際には所得額や経費計上によって変動)がかかると仮定します。
- 所得税・住民税(概算): 193.6万円 × 0.20 = 約38.7万円
税引後キャッシュフローの算出
193.6万円(税引前キャッシュフロー) – 38.7万円(所得税・住民税) = 154.9万円
このシミュレーションの例では、表面利回り10%の物件でも、税引後の手残りは年間約154.9万円となりました。これを月額にすると約12.9万円です。
自己資金1000万円を投入して、年間154.9万円のキャッシュフローが得られる。悪くない数字に見えるかもしれません。しかし、もし運営費用が想定より高かったり、空室期間が長引いたり、大規模修繕が前倒しで発生したりすれば、この年間154.9万円というキャッシュフローはあっという間にマイナスに転じ、毎月あなたの給料からお金を補填する「持ち出し物件」に化ける可能性もあるのです。
このシミュレーションで重要なのは、仲介手数料などの購入時諸費用を分母に入れず、あくまで毎年の収益性を測る指標としてNOI利回りや税引後キャッシュフローを計算することです。購入時諸費用は、物件取得に必要な資金として自己資金に含めて計算することで、最終的な投資効率(自己資金利回り)を判断する上で役立ちます。
投資判断は「キャッシュフロー利回り」で見るべき
ここまで見てきたように、不動産投資で本当に成功するためには、利回りという数字の裏側にある「キャッシュフロー」にこそ目を向けるべきです。手元に残る現金こそが、あなたの事業の生命線だからです。
NOI利回り・FCR(Free and Clear Return)
プロの不動産投資家が物件の収益性を評価する際に用いる「NOI利回り」は、前述の通り、購入価格に対する年間運営収入の割合です。ローン返済額を考慮しないため、物件自体の収益力を測るのに適しています。
一方、「FCR(Free and Clear Return)」もNOI利回りと同義で使われることが多く、これは「借入なしで物件を運営した場合、どれくらいの利回りが得られるか」を示すものです。投資判断の初期段階で、物件そのものの収益ポテンシャルを測る上で非常に有効な指標です。
キャッシュフローを重視する理由の真髄
いくら帳簿上「含み益」があっても、手元に現金がなければローン返済や突発的な修繕費に対応できません。
- 返済能力の絶対確保: 毎月のローン返済を滞りなく行うためには、安定したキャッシュフローが不可欠です。ローン返済が滞れば、最悪の場合、担保物件を差し押さえられるリスクがあります。
- 予備費(運転資金)の確保: 不動産投資には、予測不能な出費がつきものです。給湯器の故障、入居者の短期退去、隣人トラブルによる弁護士費用など、いざという時に備えるための資金を常に手元に残しておく必要があります。キャッシュフローが潤沢であれば、こうした事態にも慌てず対応できます。
- 再投資の機会創出: 蓄えたキャッシュフローを、次の物件購入資金、あるいは既存物件の設備グレードアップやリノベーション費用に回すことで、さらなる収益拡大、ひいては資産価値の向上を目指せます。キャッシュフローがなければ、成長の機会を失ってしまいます。
- 精神的安定: 毎月赤字が出て、自分の給料から持ち出しが続けば、精神的なストレスは計り知れません。キャッシュフローがプラスであれば、安心して不動産投資を継続できます。
元利均等返済後に残る「本当の手取り」が最重要
不動産投資の目的が「資産形成」であれば、ローンの元金返済が進み、資産価値が向上していくことは重要です。しかし、事業として継続するためには、元利均等返済(または元金均等返済)でローンを返済した後に、手元にいくら現金が残るのか、税引後のキャッシュフローがプラスであることが何よりも重要です。これがマイナスであれば、あなたの財布からお金が流出し続けることになり、他の投資や生活にまで影響を及ぼす「負動産」と化してしまいます。
利回りの数字だけに騙されない!プロが実践する投資判断のコツ
ここまで、利回りがいかに多面的なものであるかを理解いただけたかと思います。不動産投資は、適切な知識と戦略があれば、どのようなエリアでも成功の可能性を秘めています。大切なのは、利回りという数字を正しく使いこなし、失敗しないためのプロの実践的なコツを身につけることです。これは、多くの投資家が経験と失敗を重ねてようやく辿り着く視点です。
地方高利回り vs 都心低利回り、それぞれの「勝機」を見極める
不動産投資ではよく「地方の高利回り物件」と「都心の低利回り物件」が比較されます。どちらにもメリット・デメリットがあり、一概に優劣をつけられるものではありません。重要なのは、それぞれのエリア特性を理解し、自身の投資目的やリスク許容度に合わせて最適な戦略を立てることです。
地方高利回り物件の現実と攻略法
- 見かけの利回りの高さ: 物件価格が安い分、表面利回りが高く見えがちです。少額から始められるため、初心者にとって魅力的に映るかもしれません。
- 隠れた高リスクと対策: しかし、その裏には人口減少、働き口の少なさ、高齢化による賃貸需要の低迷、管理体制の脆弱さ(地元に良い管理会社が少ない)、そして特定の施設(工場、大学など)への依存といった潜在的なリスクが潜んでいます。
- 攻略法: 徹底的なエリアリサーチが不可欠です。特定の工場や大学、再開発計画など、局所的に人口流入や雇用創出が見込めるエリアに絞り込むこと。また、信頼できる地元の管理会社と提携し、空室対策や入居者ニーズの把握に努めることが成功の鍵を握ります。
- 空室の長期化と対応: 一度空室になると、次の入居者が決まるまでに想定以上に時間がかかり、数ヶ月から年単位の空室が続くことも珍しくありません。これにより、あっという間に実質利回りは低下し、マイナスキャッシュフローに陥るリスクがあります。
- 対応策: リノベーションによる競争力強化(例えば、築古でも水回りや設備を最新にする、インターネット無料を導入するなど)、家賃設定の柔軟性、そして複数物件所有によるリスク分散が有効です。
- 売却の困難さと出口戦略: いざ売却しようとしても買い手が見つからず、大幅な価格引き下げを余儀なくされるか、最悪の場合「買い叩かれる」リスクが高いです。
- 出口戦略: 高利回りによる短期での投資回収を目指すか、特定の企業や施設に関連する「社宅需要」など、明確な買い手が見込める市場を狙う戦略が考えられます。また、融資がつきにくい地方物件は、現金買いの投資家層がターゲットになるため、価格設定もその層に合わせて柔軟に検討する必要があります。
都心低利回り物件の真価と活かし方
- 表面利回りは低め: 物件価格が高いため、表面利回りは低い傾向にあります。初期投資額が大きくなることが多いでしょう。
- 安定した需要: 人口が増加傾向にあり、交通の便も良く、経済活動が活発な都心部では、安定した賃貸需要が期待できます。空室リスクが低く、賃料の下落リスクも比較的限定的です。
- 高い流動性: 万が一売却が必要になった場合でも、買い手が見つかりやすく、適正な価格での売却が期待できます。金融機関も都心物件には融資を出しやすいため、買える層が広がり、流動性が高まります。
- 資産価値の維持・向上: 長期的に見れば、インフレや再開発、人口流入などにより、資産価値が維持されたり、場合によっては向上したりする可能性も秘めています。これは、利回りが低くても「売却益(キャピタルゲイン)」でトータルのリターンを高める戦略が有効であることを意味します。
- 活かし方: 長期的な視点でのインカムゲインとキャピタルゲインのバランスを重視し、安定したキャッシュフローを得ながら、将来の売却益も視野に入れる投資が基本となります。
どちらのエリアを選ぶにしても、物件の特性とエリアの市場を深く理解し、それに見合ったリスクヘッジと戦略を立てることが、不動産投資を成功に導く絶対条件です。
利回りよりも「出口(売却)」を強く意識する
不動産投資は、物件を購入したら終わりではありません。いつか売却する「出口戦略」を常に意識しておくことが、トータルリターンを最大化するための最重要ポイントです。
- 売却のしやすさ(流動性): 賃貸需要が安定しているエリアの物件は、売却時にも買い手が見つかりやすいです。特に金融機関が融資を出しやすい物件は、買える層が広がるため、より早く、より高く売却できる可能性が高まります。
- 資産価値の維持・向上(キャピタルゲイン)
利回りだけを追求して、将来的に需要が激減するようなエリアの物件を選んでしまうと、いざ売却時に大幅な価格下落に見舞われる可能性があります。再開発計画がある、人口流入が続いている、あるいは特定の産業が発展しているなど、将来的な価値向上が期待できるエリアを選定することが、キャピタルゲイン(売却益)を狙う上でも重要です。 - ローンの残債と売却価格: 売却価格がローンの残債を下回ってしまうと、自己資金を持ち出して売却せざるを得ない「オーバーローン売却」となり、損失が確定してしまいます。ローン返済が進むにつれて売却益が出やすくなるため、長期的な視点での売却タイミングも考慮に入れるべきです。
長期修繕計画と大規模リフォームを「投資計画」に組み込む
物件の築年数が古くなるにつれて、大規模な修繕やリフォームが必要になるのは避けられません。これらは予測可能な費用であるにもかかわらず、多くの初心者が計上を忘れ、資金繰りに苦しむ原因となります。
- 想定外の出費を防ぐ
外壁塗装、屋上防水、給排水管の交換、エレベーターの更新など、一度に数百万円から千万円単位の費用がかかることも珍しくありません。これらの費用を計画に入れていないと、いざという時に資金が不足し、最悪の場合、物件の価値が低下したり、入居者が離れていったりする原因となります。 - キャッシュフローへの影響: これらの大規模修繕費用は、その発生年にキャッシュフローを大きく圧迫します。そのため、年間のキャッシュフロー計算に加えて、「数年〜数十年単位の長期修繕計画」を立て、必要な修繕費をあらかじめ毎年の積み立て目標として事業計画に盛り込んでおくことが不可欠です。
- 価値維持・向上への投資:
単なる修繕だけでなく、入居者のニーズに合わせた設備更新やリノベーション(例えば、築古物件でのインターネット無料化、独立洗面台の設置、TVモニター付きインターホンの導入など)は、空室対策や家賃維持、さらには家賃アップにも繋がり、結果的に物件の価値向上に寄与します。これは「費用」ではなく、未来への「投資」として捉えるべきです。
まとめ
不動産投資において、「利回り」は非常に重要な指標であることに変わりはありません。しかし、その数字の裏に隠された意味と、それを正しく活用する方法を理解しなければ、大きな失敗につながる可能性があります。
表面利回りだけを信じると失敗する理由:
- 物件の運営にかかる管理費、修繕費、税金、保険料、そして最も恐ろしい「空室」による損失など、多くの費用が一切考慮されていない、いわば「見せかけの数字」だからです。広告で高い利回りを見ても、すぐに鵜呑みにせず、一度立ち止まって、その裏にある現実的なコストを想像することが重要です。
必ず実質利回り・キャッシュフローまで計算しよう:
不動産投資で成功するために最も重要なのは、「物件を所有・運営するためにかかる全ての費用」を正確に把握し、そこから得られる「年間運営収入(NOI)」、そしてローン返済と税金を引いた後の「税引後キャッシュフロー」を計算することです。このキャッシュフローがプラスで安定していることが、あなたの不動産投資を成功へと導く紛れもない鍵となります。
「利回り」はあくまで投資を始める入り口の指標に過ぎません。その奥にある、物件の真の収益力と潜在的なリスクを深く掘り下げて分析する力が、あなたの不動産投資の明暗を左右するでしょう。この記事が、これから投資を始める方のヒントになれば嬉しいです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
岡山の不動産投資なら岡山の不動産エージェントへ
岡山での不動産投資をご検討中の方は、地域密着で豊富な実績を持つ岡山の不動産エージェントにお気軽にご相談ください。
こんな方はぜひご相談ください
- 岡山での物件探しをサポートしてほしい
- 岡山での物件売却をサポートしてほしい
- 投資収支のシミュレーションを詳しく知りたい
- 地域の最新市場動向を教えてほしい
- 融資や税務についてアドバイスが欲しい
- 全国どこでも対応させていただきます
無料相談・お問い合わせ
RE/MAX VALUE
不動産エージェント 大城 廷寛
📞 電話番号: 080-8354-1201
🏢 事務所: 086-434-6006
📧 メール: takahiro.oshiro@remax-agt.net
📋 宅建免許番号:岡山県知事(1)第6225号
お客様の理想を実現する、不動産パートナーとしてお手伝いいたします。
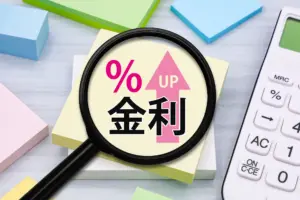


Reviews